琉球王家秘伝本部御殿手
|
本部 朝行 〒597-0015 大阪府貝塚市堀2-22-6 ■ 電話(072) 433-3821 ■ 琉球王家秘伝本部御殿手 ホームページ |
 |
由来
当流は、琉球王国第二尚氏王統第十代・尚質王の第六王子、尚弘信・本部王子朝平を始祖とし、琉球王族・本部御殿に伝えられてきた武術である。「御殿」とは王族の家柄を意味し、「手」とは武術を指す。王朝時代、本部御殿の歴代当主は、王位継承権を有する王子や按司の身位にあり、かつ武術に秀で、代々本部御殿手を継承してきた。
廃藩置県後は、第十一代当主・本部朝勇が継承者となった。弟には空手家として著名な本部朝基(本部流開祖)がいる。戦前、朝勇は息子たちへの継承を望んだが、王国滅亡後の家運の衰退とともに息子たちは本土へ移住し、継承は困難となった。このため、弟子の上原清吉を通じて、和歌山に住む次男・朝茂に伝えたが、先の大戦で朝茂が戦死した。戦後、ふたたび甥の本部朝正(朝基嫡男)に上原清吉から伝授され、その後、朝正の長男・本部朝行がこれを継承し、現在に至る。
系譜
《本部御殿手》
第十代尚質王-流祖尚弘信・本部王子朝平-二代本部按司朝完-三代本部按司朝智-四代本部王子朝隆-五代本部按司朝恒-六代本部按司朝救-七代本部王子朝英-八代伊野波按司朝徳-九代本部按司朝章-十代本部按司朝真-十一代本部朝勇-十二代上原清吉-十三代本部朝茂-十四代本部朝正-十五代本部朝行
流儀の特徴
本部御殿手では、突き蹴りを主体とした体術の稽古から始まり、次第に相手を傷つけることなく無抵抗にしてしまう「取手(トゥイティー)」と呼ばれる投げ技・関節技の修業へと進む。取手の稽古と並行して、各種武器術も修業する。武器術では、琉球王族が所持していた刀剣類のほか、箒、櫂、鳥刺し棒など日常道具も武器として使用する。このように剛と柔の技を積み重ね、やがて奥義である武の舞「舞手」へと至る。
伝承されている伝書
一 本部朝勇遺歌
一 教訓歌
活動状況
大道館(総本部)では、毎週木曜日および土曜日の午後七時より、定例稽古を行っている。国内での活動に加え、定期的に海外に赴き、本部御殿手の武術セミナーを開催し、国際的な交流と技術の普及に努めている。また、各支部においても、空手道選手権大会への出場や、地元で開催される古武道大会への参加など、地域に根ざした活動を積極的に行っている。
| ●稽古場及び支部 ▽総本部 大道館 大阪府貝塚市堀2-22-6 ▽支部 国内9支部、海外7支部 |
| ●文化財指定 |
| 本部御殿墓(令和3年、宜野湾市指定文化財<史跡>) |
 合戦ヌーチク型 合戦ヌーチク型 |
 貫手による組手 貫手による組手 |
 本部御殿墓 本部御殿墓 |
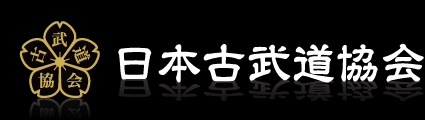
 第十五代宗家
第十五代宗家